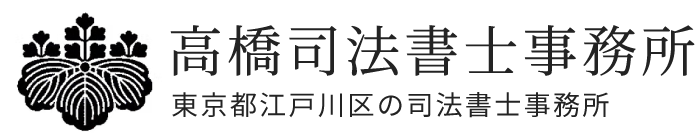FAQ

FAQ
よくある質問
Inheritance相続問題・民事信託
- 親が亡くなったのですが、名義変更に期限はありますか?
-
令和6年4月1日より相続登記が義務化となり、相続開始後3年内に相続登記をしなければ罰金(正確には過料)が課されることになりました。
しかし、相続人間で協議がまとまらず協力的な方にも過料がかかるというのは納得がいかない、と思われる場合には別途方法がありますので、詳しい事はご相談ください。
- 遺言は自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がいいのですか?
-
自筆証書遺言の場合には、遺言者の死後に裁判所に検認手続きの申請をして裁判所から相続人全員に対して呼び出しがあり、その期日で確認作業が必要となります。
それに対して、公正証書遺言はその裁判所における手続きが省略できる利点があります。公正証書遺言を作成する際に費用が発生しますが、死後の手続きを考えると公正証書遺言の方が便利といえるでしょう
- 相続放棄をすることができるのはいつまでですか?
-
最高裁は、「原則として相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から」としていますが、例外として「上記各事実を知った時から3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識志うべき時から起算すべきである。」と判断しました。
この判断は、要するに、相続人が相続財産が全くないと信じただけでなく、そう信じることについて相当な理由が必要であるとするもので、被相続人が亡くなるまでの生活の状況や相続人との交際の状態により判断されます。
できるだけ早めに相続放棄手続きをすることが良いですが、被相続人が亡くなって3カ月経過したのちも、相続放棄することができる可能性はゼロでは無いでしょう。
プラス財産とマイナス財産が詳しく判明するまでにある程度時間を要する場合には、相続放棄の期間伸長の申立をすることにより、期間を延ばすことができます。 詳しくはご相談ください。 - 遺産分割協議を兄弟間で執り行いますが、その際の注意点を教えてください。
-
遺産分割協議には、各家庭によってさまざまかと思いますが、まず協議をする前に生前に被相続人(亡くなられた方)から受け取った贈与の存否や、遺言などで受け取った財産を確認します。
その財産を「特別受益」と言って、相続分を事前にもらっていたものとして、現存の相続財産に合計して、受け取っていた者の相続分からその特別受益分を差引きます。(期限の制限があります)また生前に被相続人に対して特別な寄与した方(療養看護を特に務めた方や、被相続人の財産を増やすことに貢献したかた)に対し、その相続人はほかの相続人より多く相続分を取得する権利があります。
その権利を「寄与分」といい、今度は現存の相続財産から差し引いて、特別な寄与した相続人に対し、相続分に寄与分を足すことが認められています。そのような特別受益分及び寄与分を検討し、相続人間で公平な分割協議を行うことがよいでしょう。
但し、話し合いが整わない場合、裁判上の手続きをする必要がでてきて親族関係にとても深刻な影響を与えてしまう可能性がありますので、落ち着いて交渉してください。詳しくはご相談ください。 - 「民事信託」と「後見」はどう違うの?
-
後見人は裁判所の監督を受けることになり、次のようなことはできなくなります。
①贈与 ②金銭を貸す ③相続税対策のためにアパートを建築したり、不動産を購入すること
しかし、信託をした場合には、上記の作業を信託の目的に範囲内であれば手続きすることは問題ありません。また、後見の場合には、後見人や後見監督人に対して報酬が発生いたしますが、信託の場合には受託者への管理報酬を定めなければ報酬など費用は一切かかりません。少なくとも他人に支払うものは一切ありません。ただ信託には身上監護権が無いため、その部分を補完するために任意後見契約と併用する方もいます。※身上監護とは
成年後見人が、成年被後見人の心身の状態や生活の状況に配慮して、被後見人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行うことや、未成年者の法定代理人(親権者又は未成年後見人)が、未成年者の身体的及び精神的な成長を図るために監護・教育を行うことをいいます。 - 「民事信託」と「遺言」とはどう違うの?
-
遺言は死亡時に初めて効力が生じるもので、生前には何も効力はありません。
遺言は様式が法律で決められており、作成方法に誤りがある場合には無効になることもあります。また、自筆証書遺言の場合には、死亡後に裁判所に検認の申立てを行わないと遺言書が使用することができません。遺言の検認とは、遺言書の筆跡を法定相続人に確認いただくこと、また新しい遺言書が無いか確認する場になります。そのため、裁判所へ検認申立てた後、裁判所から法定相続人全員に呼び出し状が届き、その期日に裁判所に出向き確認する作業があります。信託の場合には、最終的な財産の帰属権利者を定めておけばその方に承継できますので、裁判所の手続きは一切不要です。また、遺言の場合には、遺言執行者の定めがない場合には、法定相続人全員の署名が必要になることがあります。信託の場合には、受託者の作業だけで全て相続手続きをすることができます。
- 民事信託には「節税」のメリットがあるの?
-
民事信託では受託者に対して財産を移転する際の流通税(不動産取得税など)はかかりませんし、委員者から受託者へ財産を渡したことによる譲渡所得税なども発生しません。
財産を移動する場合、不動産には譲渡人に対し譲渡所得税が課税され譲受人に対しては贈与税、流通税が課税されます。しかし、民事信託の場合は受託者へ財産を預けるため流通税はかかりません。民事信託では、財産を受託者へ移転しなければなりませんが、不動産の場合、所有権移転登記を行う必要があります。移転登記費用は、評価額の1,000分の4(特例あり)になります。その後委託者が死亡し受託者に承継する場合には、信託登記の抹消登記(1筆1,000円)をするだけで受託者へ承継することができます。将来的に相続登記をすることを考えると、相続登記も同率の登記費用がかかりますので、信託登記とほぼ同じ金額で所有権移転登記をすることができ、無駄な登記費用が無いとても良い制度です。
「流通税(りゅうつうぜい)」とは
資産(財産)の権利移転(所得)に課税される租税のことで、「国税→内国税→流通税」となる。
日本の税制度では、自動車重量税、登録免許税、不動産取得税、印紙税等が流通税に当たる。
Registration商業・法人登記
- 会社設立の際に必要なことはなんですか?会社設立の流れを知りたいのですが。
-
直接お話を伺うほうが解りやすいと存じますが、簡単な流れのご説明をさせていただきます。
- 会社概要の決定 (商号・目的・本店所在地・資本金・出資内容割合・役員・事業年度など)
- 定款・印鑑の作成
- 公証役場で定款を認証(電子定款)
- 資本金の払い込み
- 設立登記の申請(申請日が設立日となります。平日のみ可)
- 登記完了。登記簿謄本(履歴事項証明書)や印鑑カード・印鑑証明書が取得できます。
- 会社の設立に掛かる期間はどのくらいですか?
-
会社の形態によって様々ですが、ある程度シンプルで打ち合わせに時間を要さない場合であれば、定款作成から登記の完了まで最短で約10日から2週間くらいです。 実際は打ち合わせに細かい詰め作業もありますので、早くても3週間前後と見て頂ければと存じます。
- 会社の商号は、規制が無くなったと聞きましたが、本当に自由に他の会社と似たような商号を定める事ができるのですか?
-
商法改正により基本的に商号選定の自由になりました。限定的に一定の制約がありますが、それは同一の商号で、かつ、その本店の所在場所が、その他人の商号の登記にかかる営業所所在地と同一であるときは、することができないことになりました。従って、ほとんどの場合、規制がかからなくなりました。しかし、本当に全てが自由化になった訳では無く、登記手続き上の規制緩和だけであって、不正競争防止法や、商標権等によって依然と変わらず規制があります。他の会社と同様または似たような商号にした場合、民事紛争に発展する可能性がありますので、注意が必要です。詳しくはご相談ください。
- 会社の目的外の業務をしていますが、会社として大丈夫なのでしょうか?
-
会社とは人が法律により作り上げた人格です。その行動範囲(業務範囲)を目的で定めているわけです。従って、目的外の業務は、代表者や役員等の個人的な業務とみなされる可能性があります。損害賠償責任や、税金問題等、様々な問題に発展する可能性がありますので、早急に目的に追加することが必要です。詳しくはご相談ください。
- 役員変更登記をするのをうっかり忘れてしまいました。罰金はいくらくらいかかるのでしょうか?
-
正確には罰金ではなく「過料」という制裁になります。商業登記の多くは登記事項に変更が生じた後2週間以内に登記申請しなければならず、期間にはさまざまありますがその登記期間内に登記しなければ過料に処せられます。 この過料の制裁は、登記をしなかったことについて故意または過失がある場合に限って科される。その金額とは、個々の会社のいままでの経過、常習、内容、懈怠期間等様々な要因で科されますが、会社法976条には「100万円以下の過料に処する」とだけ規定されています。100万円とびっくりするかと思いますが、そこまで高額なケースは私どもは聞いた事がありません。多くて20~30万円位までしか聞いた事はありません。もちろん全国的に過去の例を探せばもっと高額な事例は出てくると思いますのであくまで参考程度に受け止めてください。 また、当該過料の制裁は、登記をすべき取締役又は執行役であります。対象は会社ではないため、経費に充てることはできません。